【活用率18%】個人年金保険料控除でお得に節税!仕組みとメリットを徹底解説
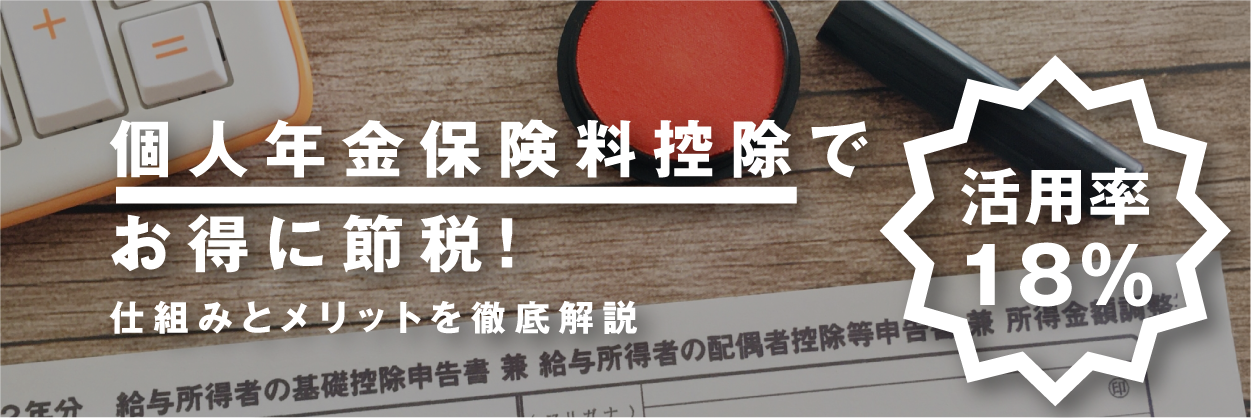
将来の生活資金に不安を感じ、「老後のために少しずつでも積み立てたい」と思っている方は多いのではないでしょうか。特に会社員や公務員の方にとって、給与から天引きされる税金の負担は決して軽くありません。「毎月の収入から差し引かれる額がもう少し減ったら、その分を貯蓄や投資に回せるのに…」と感じる瞬間もあるはずです。そんなときにぜひ知っておきたいのが、個人年金保険料控除です。
この制度は、生命保険料控除の一部として位置付けられており、個人年金保険の保険料を支払った場合に所得から一定額を差し引くことができる仕組みです。結果として、所得税や住民税の負担を軽減することができます。つまり「将来の老後資金を準備しながら、現在の節税効果も得られる」という一石二鳥のメリットがあるのです。
しかしながら、国税庁の調査によれば、この制度を実際に活用している給与所得者はわずか約2割にとどまっています。残りの約8割は、せっかく利用できる可能性があるにもかかわらず、制度を知らなかったり手続きを行っていなかったりするため、節税のチャンスを逃しているのが現状です。
本記事では、個人年金保険料控除の仕組みや計算方法、実際にどれくらい税金が軽減されるのかを具体例を交えて解説します。また、なぜ活用率が低いのか、その理由や注意点についても掘り下げます。読み終えるころには、あなた自身が控除の対象になるかどうか、そしてどうすれば正しく制度を活用できるのかを理解できるでしょう。
無料保険相談を予約する
目次
個人年金保険料控除とは?
![]() 個人年金保険料控除とは、生命保険料控除の一部に含まれる制度で、個人年金保険に加入している人が、支払った保険料に応じて所得から一定額を差し引ける仕組みです。課税所得が少なくなることで、結果的に所得税や住民税の負担が軽減されます。つまり、将来のために年金を積み立てながら、現在の節税効果も同時に得られるというメリットがあります。老後資金の準備を考える人にとっては特に有効な制度ですが、実際に活用できている人は全体の約2割にとどまり、多くの人がその存在や仕組みを十分に理解できていないのが現状です。ここでは、まず生命保険料控除の基本を確認し、続いてその中に含まれる3つの控除について整理していきます。
個人年金保険料控除とは、生命保険料控除の一部に含まれる制度で、個人年金保険に加入している人が、支払った保険料に応じて所得から一定額を差し引ける仕組みです。課税所得が少なくなることで、結果的に所得税や住民税の負担が軽減されます。つまり、将来のために年金を積み立てながら、現在の節税効果も同時に得られるというメリットがあります。老後資金の準備を考える人にとっては特に有効な制度ですが、実際に活用できている人は全体の約2割にとどまり、多くの人がその存在や仕組みを十分に理解できていないのが現状です。ここでは、まず生命保険料控除の基本を確認し、続いてその中に含まれる3つの控除について整理していきます。
生命保険料控除の基本
生命保険料控除とは、1年間に支払った保険料をもとに課税所得を減らせる制度です。通常、給与所得から社会保険料控除や基礎控除などを差し引いて課税所得を算出しますが、ここに生命保険料控除を追加すればさらに課税所得が減り、その分税金が安くなります。具体的には、所得税と住民税それぞれに上限額が定められており、例えば個人年金保険料控除であれば、所得税で最大4万円、住民税で最大2万8千円が控除対象となります※1。これにより、毎年数千円から一万円以上の税金が軽減されるケースも少なくありません。つまり「控除=節税の仕組み」であり、知らずに使わないままでいるのはもったいない制度だと言えるでしょう。
※1 2012年以降契約の新制度の場合
3つの控除の種類と違い
生命保険料控除には、新制度(2012年1月1日以降の契約)から3つのカテゴリーが設けられています。
-
一般生命保険料控除
死亡保険や学資保険など、万一に備える保険が対象です。活用率は77.5%と高く、多くの人が利用しています。 -
介護医療保険料控除
医療保険やがん保険、介護保険など、病気やケガに備える保険が対象です。活用率は62.9%とこちらも広く利用されています。 -
個人年金保険料控除
老後の生活資金づくりを目的とした個人年金保険が対象で、税制適格特約を付加した契約である必要があります。ところが、活用率はわずか18.0%にとどまっています。
このデータからも、個人年金保険料控除は他の控除に比べて圧倒的に利用されていないことが分かります。背景には「制度を知らない」「対象外の契約を選んでしまう」といった理由がありますが、正しく理解すれば節税と老後資金準備を同時に叶えられる強力な仕組みです。
無料保険相談を予約する
個人年金保険料控除の仕組み
![]() 個人年金保険料控除は、支払った保険料に応じて課税所得を減らし、その分の税金を軽減できる制度です。老後資金を準備するために加入した保険の保険料が、単なる支出ではなく「節税につながる投資」として働くのが大きな特徴です。ただし、控除額には所得税・住民税それぞれで上限が決められており、支払った金額に応じて段階的に計算されます。まずは具体的な計算方法を確認してみましょう。
個人年金保険料控除は、支払った保険料に応じて課税所得を減らし、その分の税金を軽減できる制度です。老後資金を準備するために加入した保険の保険料が、単なる支出ではなく「節税につながる投資」として働くのが大きな特徴です。ただし、控除額には所得税・住民税それぞれで上限が決められており、支払った金額に応じて段階的に計算されます。まずは具体的な計算方法を確認してみましょう。
控除額の計算方法(所得税・住民税)
新制度(2012年1月1日以降の契約)における個人年金保険料控除の上限は、所得税で4万円、住民税で2万8千円です。支払保険料の金額に応じて、次のように計算されます。
所得税の場合
- 年間2万円以下 → 支払保険料の全額
- 2万~4万円以下 → 保険料×1/2+1万円2万~4万円以下 → 保険料×1/2+1万円
- 4万~8万円以下 → 保険料×1/4+2万円4万~8万円以下 → 保険料×1/4+2万円
- 8万円超 → 一律4万円8万円超 → 一律4万円
住民税の場合
- 年間1.2万円以下 → 支払保険料の全額
- 1.2万~3.2万円以下 → 保険料×1/2+6千円
- 3.2万~5.6万円以下 → 保険料×1/4+1.4万円
- 5.6万円超 → 一律2.8万円
つまり、年間で8万円以上の保険料を支払えば、最大で所得税4万円+住民税2.8万円=合計6.8万円が課税所得から控除されます。これは支払った金額がそのまま返ってくるわけではありませんが、課税所得を減らすことで税負担を確実に軽くする効果があります。
今なら無料相談予約で
選べるデジタルギフトプレゼント! 3/3112/31 まで!
個人年金保険料控除なぜ活用率が低いのか?
![]() 節税効果と老後資金準備を同時にかなえることができる個人年金保険料控除。しかし、実際に活用できている給与所得者は全体のわずか18%程度にすぎません。一般生命保険料控除や介護医療保険料控除と比べても低い水準にとどまっており、せっかくのメリットを逃している人が大多数です。なぜこれほどまでに利用率が低いのでしょうか。その背景には制度認知の不足や、手続き上の勘違いなど、いくつかの要因が潜んでいます。
節税効果と老後資金準備を同時にかなえることができる個人年金保険料控除。しかし、実際に活用できている給与所得者は全体のわずか18%程度にすぎません。一般生命保険料控除や介護医療保険料控除と比べても低い水準にとどまっており、せっかくのメリットを逃している人が大多数です。なぜこれほどまでに利用率が低いのでしょうか。その背景には制度認知の不足や、手続き上の勘違いなど、いくつかの要因が潜んでいます。
活用率18%の現状
国税庁の「令和4年民間給与実態統計調査」によると、給与所得者のうち一般生命保険料控除を利用している人は77.5%、介護医療保険料控除を利用している人は62.9%です。これに対し、個人年金保険料控除の利用者はわずか18.0%。つまり、10人に2人しか使っていない計算になります。理由の一つは、個人年金保険そのものの加入率が医療保険や死亡保障系の保険に比べて低いことです。また、保険会社から届く「控除証明書」を提出しなければ控除が受けられないため、制度の存在を知っていても実際に年末調整や確定申告で申請し忘れてしまうケースも少なくありません。
見落としやすいポイント
利用率の低さには、読者自身も無関係ではない「盲点」がいくつかあります。
●制度そのものを知らない
「個人年金保険料控除」という名称に馴染みがなく、そもそも活用できる制度だと知らない人が多いのが現実です。
●契約内容が対象外になっている
「個人年金」と名のつく商品でも、契約者・被保険者・年金受取人が同一でなかったり、年金の受け取り開始年齢や期間が適用条件を満たしていなかったりすると控除の対象外になることがあります。
●証明書を提出し忘れる
保険会社から送付される「控除証明書」を提出しなければ、制度を利用できません。書類管理の煩雑さが活用を妨げている一因です。
これらの点は、知識不足や小さな手続きミスによって簡単に発生します。だからこそ、「自分の契約は対象なのか?」「証明書はきちんと提出したか?」を毎年確認することが重要です。
3年連続 オリコン顧客満足度調査
保険相談ショップNo.1
安心の保険相談はほけんの110番!ご予約はこちら
個人年金保険料控除を正しく活用する方法
![]() 個人年金保険料控除は、仕組みを理解し、必要な手続きをきちんと行えば誰でも活用できる制度です。しかし、条件を満たしていない契約や証明書の提出忘れといった初歩的なミスで控除を受けられない人も少なくありません。ここでは、控除を確実に受けるために押さえておきたいポイントと、プロに相談するメリットについて整理します。
個人年金保険料控除は、仕組みを理解し、必要な手続きをきちんと行えば誰でも活用できる制度です。しかし、条件を満たしていない契約や証明書の提出忘れといった初歩的なミスで控除を受けられない人も少なくありません。ここでは、控除を確実に受けるために押さえておきたいポイントと、プロに相談するメリットについて整理します。
控除証明書と提出の流れ
まず重要なのは、保険会社から送られてくる「控除証明書」を必ず提出することです。これは個人年金保険の契約者に毎年秋頃から届く書類で、支払った保険料の金額が記載されています。年末調整の場合は勤務先に、確定申告の場合は税務署に添付して提出することで控除を受けられます。提出し忘れると控除は一切適用されないため、届いたらすぐに保管場所を決めて管理しておくことが大切です。
また、契約内容が控除の条件を満たしているか確認することも欠かせません。契約者・被保険者・年金受取人が同一人物であること、年金の受け取り開始年齢が60歳以上であること、受給期間が10年以上であることなどが主な要件です。これらを満たしていなければ「個人年金」と名前が付いていても控除対象にならない場合があります。
プロに相談するメリット
制度を正しく使うためには、保険や税制に詳しい専門家に相談する事も有効です。例えば、保険代理店やファイナンシャルプランナーは、数多くの保険商品からライフプランに合った契約を提案してくれるため、自分一人では気づけない最適なプランを選ぶことができます。さらに、控除証明書の扱いや手続きの流れについても具体的にアドバイスを受けられるので、申請漏れを防ぐことができます。
特に「老後の資金準備をどれくらいすれば安心か分からない」「どの保険商品を選べば控除の対象になるのか不安」という方にとって、プロのサポートは大きな安心につながります。自分に合ったプランを選び、正しく控除を申請することで、節税効果と将来の備えを同時に手に入れることができるのです。
無料保険相談を予約する
まとめ

個人年金保険料控除は、生命保険料控除のひとつとして位置づけられ、個人年金保険の保険料を支払った際に課税所得から一定額を差し引ける制度です。総所得から基礎控除や社会保険料控除だけでなく、この控除を加えることでさらに課税所得が低くなり、その分所得税や住民税の負担が軽減されます。つまり、制度を知っているかどうかで家計に差が生まれるのです。
2012年以降の契約から適用される新制度では「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類が設けられています。しかし国税庁の調査によると、一般生命保険料控除(77.5%)や介護医療保険料控除(62.9%)に比べ、個人年金保険料控除はわずか18.0%と非常に低い活用率にとどまっています。制度を正しく理解していない、手続きが煩雑に感じられるなどの理由で、多くの人がメリットを逃しているのです。
「自分も個人年金保険料控除を使えるのか知りたい」「どの商品を選べばよいか分からない」――そう感じた方は、専門家に相談するのが最も確実な方法です。保険相談サービスの「ほけんの110番」では、40社以上の保険会社の商品を比較し、あなたのライフプランに最適な提案を行います。
【ほけんの110番の特長】
- 相談方法が選べる:店舗での面談に加え、自宅やカフェへの訪問、オンライン相談も可能。
- お子様連れでも安心:キッズスペースを完備している店舗もあり、家族で気軽に相談できます。
- 信頼の実績:日本生命グループの一員として業界基準を満たし、安心できる品質で対応。
毎年の年末調整で「もっと税金が安くならないかな」と思っているなら、個人年金保険料控除を検討する絶好の機会です。老後の備えと節税を同時に叶えるために、ぜひ「ほけんの110番」の無料相談を活用してみましょう。
ご相談のご予約は、お電話またはWebサイトから承っております。経験豊富なスタッフが、あなたの大切な保険選びをしっかりとサポートいたします。
\全国120拠点以上の相談窓口/





